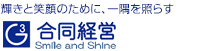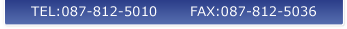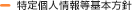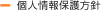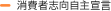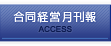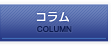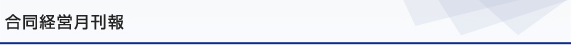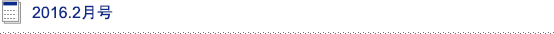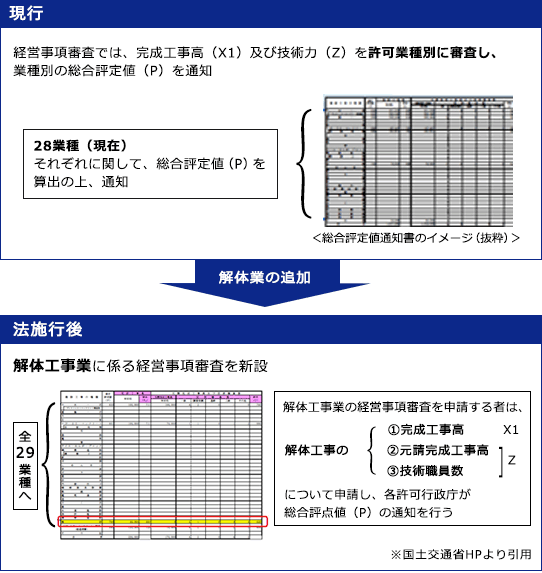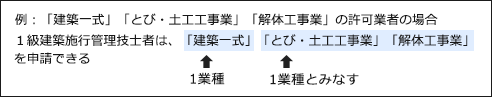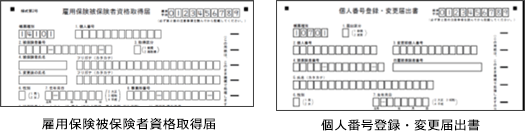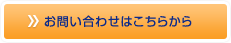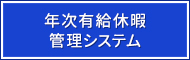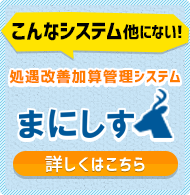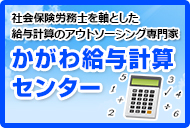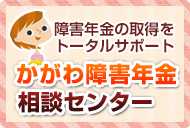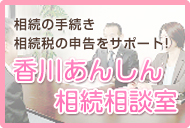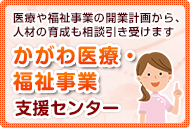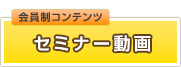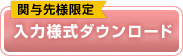今がチャンスです! 企業内人材育成推進助成金
~社内の人材育成を検討している企業におすすめです~
企業内人材育成推進助成金は、職業能力評価、キャリア・コンサルティング等の人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対して助成する制度です。
本制度は、平成27年度末(平成28年3月31日)をもって縮小が予定されていますのでぜひこの機会にご検討下さい。
- このような企業様におすすめです!
- ○社員の職業能力向上で助成金を受給したい
- ○制度導入によって求人PRに生かしたい
- ○社員の仕事に対する意識を高めたい
- ○技能検定の受検を促進したい
- ○技能伝承のために仕事の体系化をしたい
- ○従業員の定着率を高めたい
- ○従業員に対する適正な評価をしたい
各制度導入のメリット
(教育訓練・職業能力評価・技能検定合格報奨金制度)
- ・
- 社員の職業能力・モチベーションを向上させる
- ・
- 職業能力評価の結果などを活用して、適材適所の配置や公正な処遇の決定を行うことができる
(キャリア・コンサルティング制度)
- ・
- 社員が自らキャリア・プランを考える事により、仕事に対する主体性を向上させることができる
- ・
- 定年退職者などの再就職支援や、育児休業者などの職場復帰を円滑に行うことができる
【対象となる人材育成制度及び助成金額】
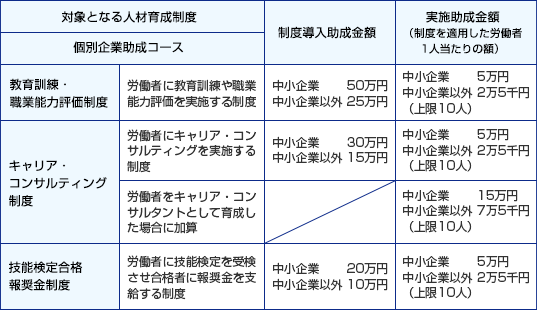
・(注1)実施・育成助成は制度ごとに10人までです。
・(注2)訓練受講者の教育訓練の受講時間数が計画時間数の8割未満の場合、支給されません。
合同経営では、計画、申請手続の代行のほか、ジョブ・カードを活用した社内評価制度の作成をサポートいたします。ぜひご相談ください。
平成28年度 税制改正大綱
平成28年度の税制改正大綱が平成27年12月に公表されました。消費税の軽減税率制度の導入などいくつかの注目すべき点がありますが、ここでは法人税等にかかる主な改正内容を挙げてみました。
【法人税】
〈実効税率の引き下げ〉
平成27年度改正に引き続き、法人実効税率が下がりますが、資本金1億円以下の中小法人は、 事業税所得割の税率変更がないため、引き下げ幅は小さくなっています。なお、課税所得800万円以下の実効税率は基本的に変更ありません。
| 中小法人(資本金1億円以下・課税所得800万円超) | |||
| 事業年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成30年度 |
| 実効税率 | 34.33% | 33.80% | 33.59% |
| 引き下げ幅 | - | △0.53% | △0.74% |
〈減価償却の見直し〉
法人税率引き下げの代替財源として建物付属設備と構築物の減価償却について定率法が適用できなくなります。
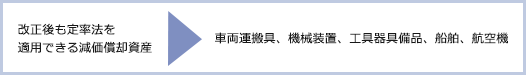
〈生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止〉
平成26年度改正で創設された、生産性向上設備にかかる特例措置は期限どおり縮減・廃止されます。
| 区分 | 平成28.3.31まで | 平成29.3.31まで |
| 機械装置等 | 即時償却又は5%税額控除 | 特別償却50%又は4%税額控除 |
| 建物、構築物 | 即時償却又は3%税額控除 | 特別償却25%又は2%税額控除 |
【その他】
〈機械装置に係る固定資産税の軽減〉
資本金1億円以下の中小法人等が、生産性を向上させる一定の機械装置を取得した場合の固定資産税(標準税率1.4%)が、最初の3年間半分に軽減されます。
解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正について(案)
建設業の許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が設けられました(平成26年6月公布、平成28年6月施行予定の建設業法改正)。
経営事項審査の経過措置
- ○
- 解体許可の取得有無に関係なく、「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、「とび・土工工事業」「解体工事業」の総合評定値も算出し通知が受けられます。(平成28年6月1日から3年間)
- ○
- 技術職員数の評価についても不公平をなくすため、「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の双方を申請しても1の業種とみなされます。(通常、技術職員1人につき申請できる業種は2業種までとしているところ、当該ケースに限り、3業種まで申請できます)
なお、経過措置により施行日(平成28年6月予定)時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要になりました
◆マイナンバーの記載が必要になった届出
(1)事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
(2)事業主が従業員の代理人として提出するもの
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
③介護休業給付金支給申請書
◆マイナンバーの記載が出来なかった場合
事業主は、雇用保険法に基づき雇用保険手続きの届出に併せてマイナンバーを届出ることが義務付けられており、従業員にも、このことを説明の上、マイナンバーの記載が必要です。
従業員の拒否などにより、記載が困難な場合は、マイナンバー記載欄が空欄でも受理してもらえます。
また、旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合でも何らかの理由により個人番号を記載できない場合には、後日「個人番号登録・変更届出書」により個人番号の提出が必要です。